INITIATIVE
企業による取り組み
2025.09.30
野村不動産株式会社
Voices for Marriage Equality Vol.1 ― 野村不動産株式会社 ー対話から学ぶ「ボウリングの“一番ピン”から倒すこと」

今年9月1日にグランドオープンを迎えたばかりの「BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S」。その15階に上ると、空と海が交じる大きな窓が現れ、息をのむほどの解放感に思わず圧倒された。野村不動産株式会社にとって、1978年より本社を構えていた新宿野村ビルから、実に47年ぶりの本社移転だという。
真新しい会議室に入るなり、同社でサステナビリティ推進を担当する執行役員の宇佐美直子さんは、ユーモアたっぷりに言った。
「93年入社の55歳。一度も転職していない、いわば“化石”みたいなものですよ。」
営業畑を長く歩き、2022年4月にD&I推進を“突然”託された。関心も知識もゼロからの出発だったという。
隣には、水天一碧株式会社代表の大嶋悠生さん。元なでしこリーグ女子サッカー選手で、トランスジェンダー男性であるバックグラウンドから“はざまから世界を見る”をテーマに企業・自治体・学校まで幅広く対話を続け、宇佐美さんと共に野村不動産株式会社でもD&I推進の立役者として携わる。
そして、婚姻の平等(同性婚の法制化)をテーマに掲げる公益社団法人「Marriage For All Japan – 結婚の自由をすべての人に」代表理事・弁護士の寺原真希子さん。
婚姻の平等に賛同する企業を可視化するキャンペーン「Business for Marriage Equality」に業界のリーダーとして名を連ねる野村不動産株式会社。その賛同に至るまでのD&I推進の歩みと、その根底にある思想に迫った。
対話を重ねた先に見えてきた、D&I推進の道しるべ
ーーD&I推進の活動は、まずはどこから始まったのでしょうか。
宇佐美:まずはそもそもD&Iって何なのか、どうしてやるのか、つまるところ何することなのか。こうした素朴な疑問に答えられるような“憲法”をまずは作ろうということで『野村不動産グループ ダイバーシティ&インクルージョン推進方針』を策定したんです。
その方針の中でも、特に「誰もがマジョリティである面とマイノリティである面の両方を持ちうることを認識し」という文章には、かなりこだわりまして。
あなただって、自覚がないかもしれないけれど、場面が変わったらマイノリティになることもあるんですよ、ということを言いたかったんです。
ーーたしかに、D&Iは“自分とは違う弱い立場の人のため”と思うと、どこか遠いものに感じてしまう方もいます。一方で、気づかないうちにマジョリティの側にいて、“マイノリティが感じている壁”に気づかずに過ごしている人も、少なくないはずですよね。
寺原:そうかもしれません。婚姻の平等も「マイノリティの人がかわいそうだから助けよう」という発想で進めるものではないと考えています。
マイノリティとされる人がマジョリティと同じ権利を得ることができる社会であれば、将来、自分自身が仮にマイノリティの立場になったときにも平等に扱われることにつながるのではないか、と。婚姻の平等は決して一部の人のためではなく、社会全体に公平さを広げるもの、そして社会を豊かにするものだと思っていますし、そのことを伝えたいと日々取り組んでいます。

宇佐美:推進方針の中ではもう一つ「すべての従業員が、自分は受け入れられていると感じることができる企業文化を醸成します」というところにもこだわりました。
よく“互いの違いを尊重し合う”といった言葉がありますが、「誰かを尊重しなさい」ではなく“自分が受け入れられていると感じられる“ことが大切だと伝えたかったんです。
この文章に至るまで、本当に何度も対話をしました。経営会議や役員会で文章を出しては直し、みんなで語り合って。すると「子どもの頃、髪の毛の色を理由にいじめられたことを思い出した」と話す人がいたり、「子どもの保護者会で居場所がないと感じた」という経験を語る人がいたり。こうした声を文章に盛り込もうという話になりました。すごくいいプロセスだったなと思っています。
大嶋:伝え方ひとつで、受け取られ方は大きく変わると思うんです。ダイバーシティの取り組み、特にLGBTについては、この10年で確かに進んできました。しかし一方で「よかれと思ってやっているのに、なんだか押しつけられているように感じてしまう」という人もいると思うんです。
だからこそ「自分もあなたと同じ人間」「自分が受け入れられると感じられることが大切」というメッセージは、とても大切だと感じています。
今まで、こうした話題は“マイノリティ側”と“マジョリティ側”という枠組みに分けて話されることも多かった印象です。でも、言葉選びを少し変えるだけで“自分の話”になっていくんですよね。

ーーさまざまな方々の言葉を吸い上げながらD&I推進方針をつくられたと伺い、とても興味深いです。役員の方々から主体的に意見を引き出すために、どのような工夫をされていたのでしょうか。結構、ここで悩んでいるD&I担当者も多いと思うんです。
宇佐美:やっぱり、分かってほしいことがあるなら「分かってくれてるな」と思えるまでとことん話すしかないと思います。これはうちの文化かもしれませんが、大勢で議論するし、メンバーの一人ひとりとも必ず話すようにしています。
弊社では、グループCEO自身がサステナビリティ委員会やD&I委員会の委員長を務めていて、CEOの部屋に行くと自分で模造紙に付箋を貼りながら「会社はどこに向かうのか」「なぜこれをやるのか」と考えているんです。「ちょっと壁打ちしようよ」と、2人で議論を重ねる。そういうやりとりを、本当に全員としつこいくらい繰り返すことができたのが大きかったと思います。
支援だけでなく、“価値創造”としてのD&Iのあり方
ーー具体的なD&I推進の活動についてもお聞かせいただけますか。
宇佐美:D&Iを企業で取り組むとなると、どうしても“マイノリティへの支援”という色が強くなりますが、私はむしろこうした活動は“価値創造”だと捉えるのが大切だと思っています。弊社は民間企業ですから、その活動がどう企業価値につながるのかという視点が不可欠です。
そこで重視しているのが、“インクルーシブデザイン”です。たとえばこのビルでも、車いすユーザーの方や視覚障害の方と一緒に浜松町駅からここまで一緒に来て、通りにくいところがないかなどをフィードバックいただくワークショップをして、事業に組み込んでいます。こうしたワークショップを行うことで、その過程で“価値創造”を体現していきたいと考えています。大嶋さんにもご活躍いただいてますよ。
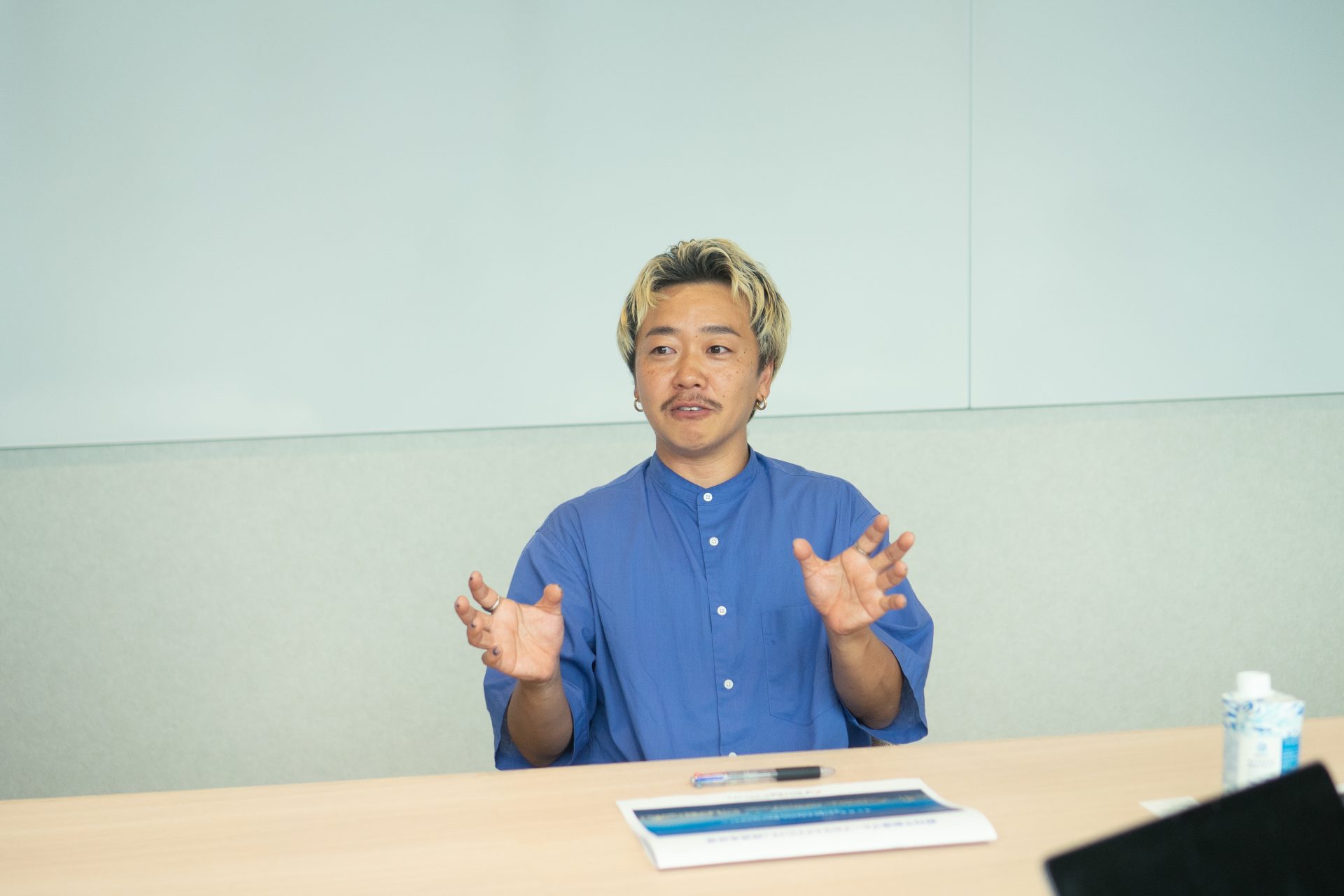
大嶋:LGBTコミュニティの人たちに集まってもらって、新しいビルに必要なコンセプトを考えようというワークショップのときには、思いもよらない結論に至ったんです。
こうしたワークショップでは、どうしても「当事者としてどう思うか」という視点ばかりになりやすいですが、大切なのは「人としてどう扱われるか」ということなんじゃないかと。
たとえば「買い物に行ったときに、LGBT当事者が買い物しやすい接客って何ですか?」と聞かれると、結局それは“心地よい接客”じゃないですか。
“誰にとっても心地よい接客”が、結局誰にとっても買い物しやすいということになる。結局“人として”大切にされるというところが、やっぱり大切なんじゃないかと。
ーーどんな人でも、ここで困ったら助けてもらえる、大切にしてもらえる実感が持てる場が大切なのではないかと感じました。まさに推進方針にも書かれた「自分が受け入れられていると感じられる」文化の醸成ですね。
寺原:まさにそうだと思います。大嶋さんがおっしゃるように、結局は人として大切にされるということが着地点になりますよね。ただ現実にはトランスジェンダーであるが故に困りやすいこと、同性愛者であることで困りやすいこと、男女の賃金格差など、属性に基づく課題はまだ残っています。だからこそ、“人としての尊厳”を土台にしつつ、それを制度でしっかり支えられるようにしていくことが大切だと感じています。
制度で言うと、私は、婚姻の平等は5年以内に実現できると信じています。そして10年後に振り返ったとき「昔の日本では同性婚が認められていなかったなんて信じられない」と言えるようになるはずです。女性の参政権が戦後になるまで認められなかったことについて、今では誰もが「そんな時代があったのか」と思うように。
不合理な理由で奪われている権利を回復させるべく、市民の力で制度を変えることができれば、「不可能だと思っていたことも、みんなで力を合わせれば変えられる」という前例になります。それが、次の挑戦への勇気にもなるといいですよね。
ボウリングの“一番ピン”を倒すイメージで
宇佐美:D&Iの意識づけを進めるうえで、最初の一歩をどこから踏み出すかを社内で議論しました。 そこで使ったのがボウリングのイメージ図です。センターのピンを倒せば、後ろのピンも連鎖的に倒れていくように、まずは“一番ピン”を明確にしようと考えたんです。
私たちがその“一番ピン”に設定したのは、育休取得率100%と有給取得目標取得の達成でした。
ーーなるほど。休暇の話であれば、多くの社員に「自分にも関係があることだ」と感じてもらいやすいですね。
宇佐美:そうなんです。実際に取り組むと、2023年3月時点で男性の育休取得率は38%だったのが、半年後には104%に(複数回取得者を含む)。
そして、育休を取る人が増えると「部署に人が足りないじゃないか」と課長から声が上がります。でも、それこそが狙いで。誰がいつ抜けても回る“強靭な組織”をつくる必要性を肌で感じてもらうきっかけになったんです。
ーーすごい。まさにボウリングの“一番ピン”を倒したことで、連鎖的に意識と行動が広がっていったんですね。
宇佐美:もうひとつ大きかったのは、今年初めて東京プライドへ出展したことです。最初は「社内理解がまだ十分でないのに、出展するなんて」と、私自身が慎重でした。婚姻の平等(同性婚の法制化)に賛同する企業を可視化するためのキャンペーン「Business for Marriage Equality」(以下、BME)への賛同も同様で、理解が追いつかないうちに表明することへの抵抗感が強かったんです。
それでも小さく一歩を踏み出したところ、社内外で反響が広がり、グループ会社から「うちも参加したい」と次々に声が上がりました。結果的に役員会でも取り上げられ、D&Iの推進が大きく前進しました。活動を社外に広げることで、社内の理解も進むことを実感しました。

ーーそれもボウリングの“一番ピン”を倒したことで、だんだんと広がっていったんですね!この戦略、いろんなところで使えそうです。
大嶋:少し似ているんですが、企業から「LGBTについて理解を推進したい」というご相談をいただくとき、私は元女子サッカー選手ということもあって、よくサッカーにたとえて考えます。
サッカーは一直線にゴールを狙うものじゃないんです。そのルートって、相手の守りが一番堅いルートなんですよね。だからこそ、まずはいくつもパスをつないで守りを崩し、タイミングを見てゴールを決める。
D&Iの取り組みも同じで、いきなりゴールを決めに行くのではなく、企業によってどのルートを通るか、どんな順番で進めるかを考えることが重要だと思って、そこに私は一番頭をつかっています。ボウリングの“一番ピン”の話にも通じますよね。
ーー婚姻の平等に関して企業が果たす役割について、どのようにお考えでしょうか。賛同していない企業もまだ多い中で、企業の役割は何だと思われますか?

寺原: 先ほど、外に発信することで社内にも返ってくるという話がありましたが、まさにそうだと感じています。ある企業がBMEへの賛同をプレスリリースやホームページで発信したとき、当事者の方からもそうでない方からも反響がありました。
たとえば転職活動中の人がそれを見て「この会社は法制度にまで踏み込んで賛同している。性的マイノリティへの取組みを本気でやっているんだ」と感じて入社を決めた、という話を何度も耳にしています。性的マイノリティではない方でも「例えば将来、自分が介護や病気などで働き方を変えざるを得ないときがきたとしても、この会社なら個々の社員に寄り添ってくれるだろう」と信頼につながることもあるようです。つまり、企業のBMEへの賛同表明は、求職者や社員にとっての安心や信頼の象徴にもなっているんです。
――企業の賛同が、人材採用や信頼にまで影響しているのはすごいですね。社会への働きかけという点では、どんな意味があるのでしょうか。
寺原: 企業による賛同は司法や立法への働きかけとしても大きな意味があります。結婚の自由をすべての人に訴訟(同性婚訴訟)の判決文には「何百社もの企業が同性婚に賛同している」ということが認定事実として記載され、社会は支持しているのに法制度だけが遅れているという違憲判断の根拠の一つにもなっています。
実際、日本のこの動きは海外からも評価されていて、韓国など同様の活動をしている団体からも「日本では大企業の賛同がこれほど広がっていて素晴らしい」と言われることがあります。企業による賛同表明は、国内だけでなく、国際的にも影響を与え得ると感じています。

「トランスジェンダーの方、障がいのある方、外国籍の方…多様なあり方が広がる中で、結局“友達を作らないと分からない”と思い、出会ったのが大嶋さんでした。
偉い人でも、先生でもなく、『ねえねえ』って話せる友達にならないと、本当に自分ごとにはできない気がして。そう思って探していたら、出会えたんですよね。」
そんなふうに語る宇佐美さんの言葉が、印象的だった。
突然D&I推進を任されて、どうしたらいいか迷う人もいるだろう。“対応を間違える”ことを恐れて、立ち止まってしまうこともあるかもしれない。
けれど、大切なのは、いきなり重すぎるボウリングボールでストライクを狙うことではなく、最初の“一番ピン”を見つけることではないだろうか。
それは友達をつくることかもしれないし、まだ知らない誰かに「ねえねえ」と話しかけてみることかもしれない。小さな始まりが、気づけば次へとつながっていく。その連なりの先に、ひいては大きな社会の変化が広がっているのだろう。
文・合田文(パレットーク編集長)
写真・中里虎鉄
企画・岩村隆行




